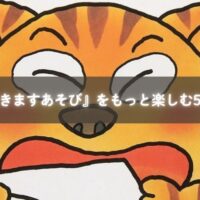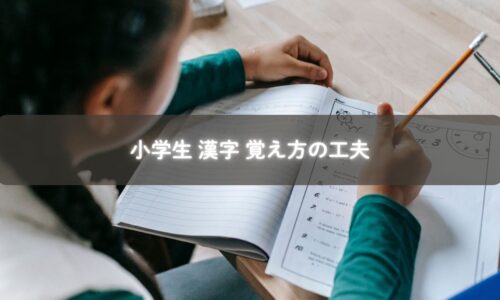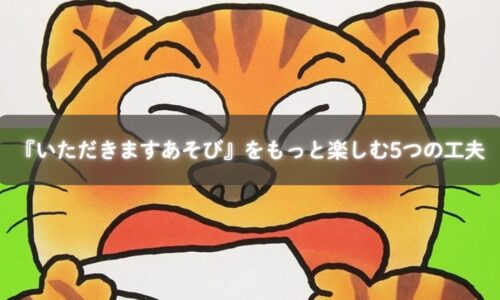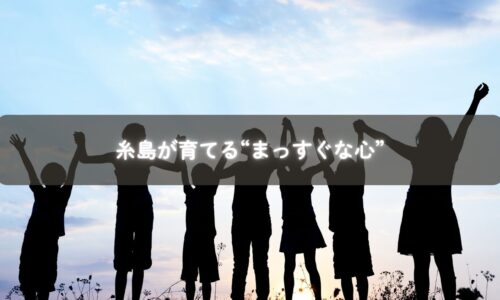幼児の英語教育はいつから?家庭で始めるベストタイミングとは?
英語教育、いつから始めたらいい?
「幼児に英語教育、いつから始めるのがいいの?」 あなたもそんな風に悩んだことはありませんか?
私も同じように迷いました。 早ければいいのか、無理にやらせたら逆効果なのか、 焦る気持ちとモヤモヤが混ざってしまって…。
でも、だからこそ、知ってほしいんです。 実は、幼児の英語教育には“今”というベストタイミングがあることを。
幼児の脳にぴったりな時期とは?
まず前提として、幼児期の脳は「音のシャワー」を素直に吸収します。 言葉をスポンジのように覚えていくのはこの時期ならでは。 特に、3歳〜6歳の間は耳の黄金期と呼ばれていて、 ネイティブの音にも驚くほど順応していくんです。
だから、「完璧に話せること」よりも「英語が身近で楽しいこと」が大切。
ママが一緒にワクワクして取り組める環境こそが、最高の教材なんです。
おすすめのスタート方法は?
とはいえ、いきなり英会話教室に通わせたり、 教材を揃えたりする必要はありません。
たとえば、おうちでできる英語の歌を流したり、 英語の絵本を読んであげたり、
YouTubeの良質な幼児向け英語チャンネルを一緒に観るだけでもOK!
まずは「英語=楽しい!」という感覚を育てることが大切。 それが、将来どんな学びにもつながっていくんです。
そして、私が、ずっと大切にしてきたのは 「日本の土台+世界の言葉」という視点。
どちらかだけではなく、両方を大切にすることで、 未来を生き抜くチカラが育つと信じています。
自分らしい子育てを始めたいあなたへ
「ママと子どもの元氣ラボって、どんな場所なんだろう?」と気になったあなたは、
こちらの紹介ページから代表の想いや活動内容をぜひ覗いてみてください。
さらに、子育ての悩みを今すぐ相談したい方は、
公式LINEにご登録いただくと、無料相談をご利用いただけます。
あなたの子育てがもっと楽になるヒントが、ここからきっと見つかります。